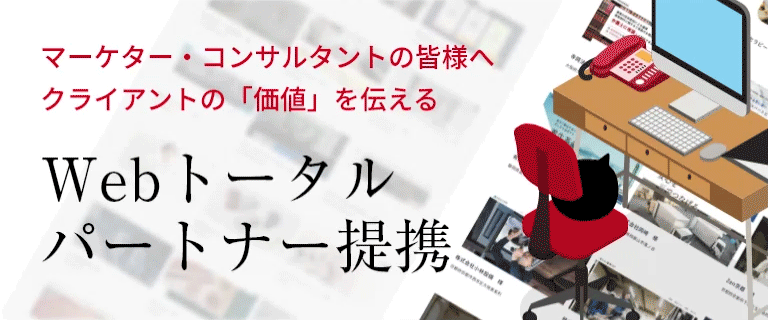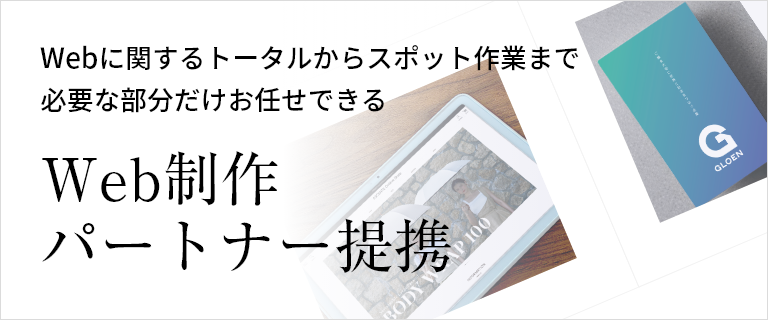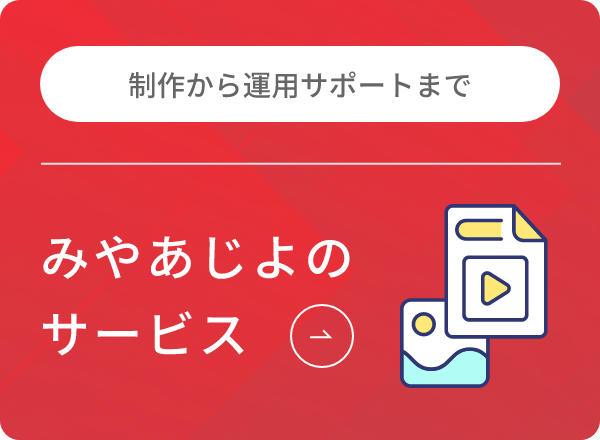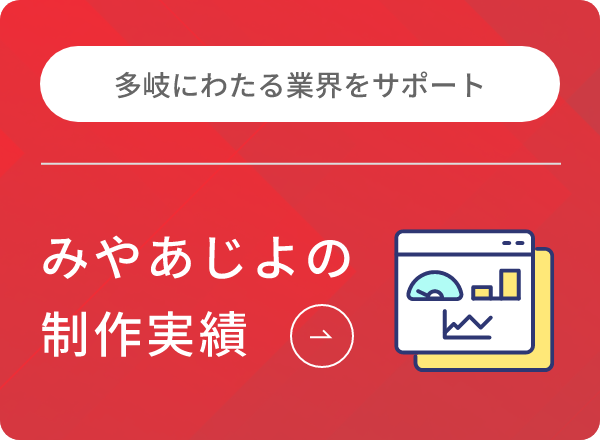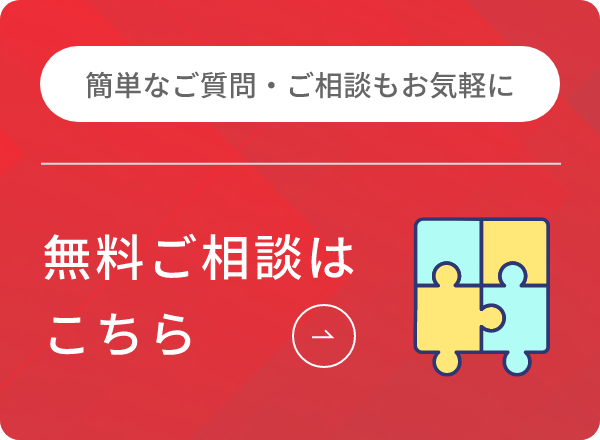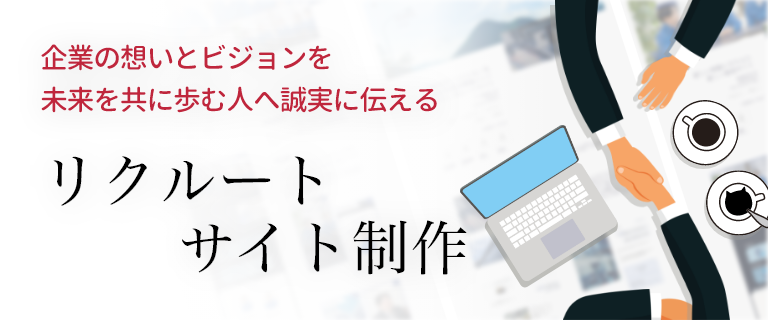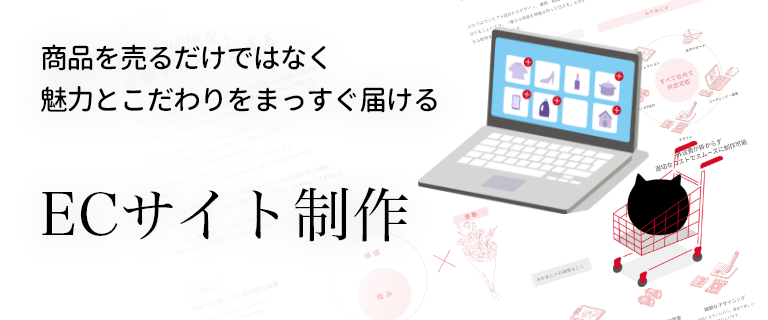クラウドファンディングと一口に言っても、色々種類がありすぎてわからない…
今回の記事はそんな方に向けたおすすめのクラウドファンディングを5つ紹介いたします。
目次
おすすめのクラウドファンディング5選
おすすめのクラウドファンディングは次の5つです。
- CAMPFIRE
- Makuake
- READYFOR
- えんfunding
- きびだんご
それぞれ詳しく解説します。
1.CAMPFIRE
CAMPFIRE(キャンプファイヤー)とは、主に購入型や寄付型に対応している国内では最大級のクラウドファンディングサイトです。
ただ、CAMPFIREグループは、エンタメ関連に特化した「BOOSTER」や、ふるさと納税に特化した「CAMPFIREふるさと納税」など、ジャンルに特化した様々なクラウドファンディングを運営しています。
そのため、自社の案件に適したサイトで資金調達が可能です。
2.Makuake
Makuake(マクアケ)とは、自治体と連携して寄付型のサービスも展開しているクラウドファンディングサイトです。
運営している株式会社マクアケの親会社はサイバーエージェントであり、集客力に定評があります。
また、国内大手のクラウドファンディングサイトの中でもCAMPFIREに次ぐ地位にあり、幅広いジャンルの案件が公開されているのもMakuakeの特徴です。
3.READYFOR
READYFOR(レディーフォー)とは、日本ではじめてクラウドファンディングサービスを開始したサイトで、2万件を超える案件と、200億円を超える支援実績があります。
カテゴリは国際協力や教育、街づくりなどが充実し、特に社会貢献や地域創生のジャンルが強いです。
4.えんfunding
えんfunding(エンファンディング)とは、不動産投資家型のクラウドファンディングサイトで、株式会社えんホールディングスが運営しています。
えんfundingで取り扱っているファンドは福岡を中心とした人気デザイナーズマンションが対象となっており、方式は優先劣後方式を採用しています。
30年以上の実績がある総合不動産デベロッパーが運営するサイトかつ、優先劣後方式の採用によって、リスクを低減しながら投資が可能です。
5.きびだんご
きびだんご(kibidango)とは、案件成功率が80%以上の購入型クラウドファンディングサイトです。
手数料は業界最低水準の10%と費用負担が少ない他、様々な分野に精通する専門家が案件を支援してくれるため、成功率の向上が見込めます。
また、GREEN FUNDINGとの同時開催も可能なため、両クラウドファンディングサイトの支援者に訴求が可能です。
クラウドファンディングを比較する際のポイント
クラウドファンディングを比較する際のポイントは次の5つです。
- 案件の成功率
- サイトにかかる利用手数料
- 得意な種類・ジャンル
- サイトの支援者数
- 審査・入金のスピード
それぞれ詳しく解説します。
案件の成功率
クラウドファンディングの国内成功率は30%程度だといわれています。
しかし、クラウドファンディングによっては成功率が80%程度のものもあるため、案件成功率が高いサイトを選べばプロジェクトを加速度的に推進することも可能です。
ただし、クラウドファンディングによって得意とする種類・ジャンルがあり、支援者数の規模も異なります。
そのため、成功率が高いからといって、自社と相性がよいというわけではありません。
サイトにかかる利用手数料
クラウドファンディングは原則、着手金はありません。
しかし、案件が成功してはじめて費用がかかる仕組みのため、調達金額に対して一定割合で利用手数料がかかります。
クラウドファンディングの利用手数料は調達額の5~10%程度ですが、サイトによって手数料は異なる他、設定次第では決算料金を含むなど、内容は大きく異なります。
そのため、クラウドファンディングを利用する際は、手数料割合だけでなく、どこにどのくらいの手数料があるかを確認したうえでサイトを選ばなければなりません。
得意な種類・ジャンル
クラウドファンディングはサイトによって得意な種類・ジャンルがあります。
具体的には種類が寄付型や購入型など、ジャンルはエンタメ系や販売系などが挙げられます。
クラウドファンディングを利用する際は、立ち上げる案件がどの種類なのか、どのジャンルなのかを明確にしたうえで、自社の案件と相性がよいサイトを選ぶことが大切です。
サイトの支援者数
サイトの支援者数つまり、クラウドファンディングのユーザー数もサイト規模を把握する重要な指標です。
サイトの支援者数が多い方がアプローチできる人数も増えるため、その分調達金額や成功率も高くなります。
しかし、サイトの支援者数が多くても、ユーザー属性が自社の案件とマッチしていなければ意味がありません。
例えば、食べ物に関心が強い支援者が多いサイトで、ガジェット関連の案件を立ち上げたとしましょう。
この場合、相性が悪いため、どれだけ素晴らしい内容であっても成功率はどうしても低下してしまいます。
そのため、支援者数だけでなく、立ち上げる案件に適したユーザー属性であるかどうかも重要なポイントとなります。
審査・入金のスピード
審査・入金のスピードもクラウドファンディングを選ぶ際の重要なポイントです。
審査が遅いと案件の掲載時期が遅れ旬を逃してしまうリスクがある他、サイトで案件が公表されないため、資金調達もスタートしません。
また、目標額を達成し案件が成功しても、入金のスピードが遅ければ手元に資金がないため、事業の開始時期が遅れてしまいます。
そのため、審査・入金のスピードが早い、クラウドファンディングを選ばなければなりません。
そもそもクラウドファンディングとは?
クラウドファンディングとは、「クラウド(群衆)」と「ファンディング(資金調達)」を組み合わせた造語です。
クラウドファンディングを活用すれば、インターネットを介して不特定多数の人々から少額ずつ支援もらいながら、資金を調達できます。
資金調達の方法は、金融機関からの融資や、ベンチャーキャピタルによる出資などが一般的でした。
クラウドファンディングは従来の資金調達にはない、手堅さやハードルの低さ、拡張性の高さから近年注目されている資金調達方法です。
クラウドファンディングの4つのメリット
クラウドファンディングを活用するメリットは次の4つです。
- 資金調達を迅速に実施できる
- 事業育成に貢献できる
- 商品・サービスを周知できる
- 商品の改善につなげられる
それぞれ詳しく解説します。
1.資金調達を迅速に実施できる
従来の融資方法と比べると迅速に資金調達できるのが、クラウドファンディングのメリットです。
銀行融資などの場合、融資の相談・審査などが必要となるため、資金を調達するまでにどうしても時間がかかります。
一方、クラウドファンディングはユーザーがいいと感じたら資金を出してくれるため、迅速な資金調達が可能です。
ただし、案件公開前に資金調達に必要な時間を決めておかないと、資金調達を正しく実施できない可能性もあるため、注意しなければなりません。
2.事業育成に貢献できる
事業育成に貢献できるのもクラウドファンディングのメリットです。
クラウドファンディングを上手く活用すれば、大規模な投資につながる他、予想以上の金額で出資される可能性もあります。
想定以上の額で出資してもらえれば、研究開発の幅が広げられ、投資家とのつながりによって様々なサービス実現が可能です。
また、クラウドファンディングを活用すれば、期待できるサービスに出会える機会も増えます。
新規投資先に出会える確率が高まるという観点から、投資家にもメリットがあります。
3.商品・サービスを周知できる
商品・サービスの周知ができるのも、クラウドファンディングのメリットです。
銀行融資などの場合は資金調達がメインであるため、資金調達と並行して商品・サービスの宣伝についても別途検討しなければなりませんでした。
一方、クラウドファンディングに案件を公開すれば、それ自体が商品・サービスの宣伝となるため、資金調達と宣伝を両立させられます。
4.商品の改善につなげられる
商品の改善につなげられるのも、クラウドファンディングで享受できるメリットの1つです。
資金調達失敗後、提供される様々なフィードバックを受けることで、問題点がどこなのかしっかりと考えながら行動できます。
問題点を把握ししっかりと改善した状態でクラウドファンディングを実施すれば、資金調達を実現する確率向上が可能です。
ただし、フィードバックを受けても、改善する方向性を間違えてしまうと思っていたような結果にならない可能性も少なくありません。
改善する際は方向性を間違えていないかを確認しながら、進めていく必要があります。
クラウドファンディングの2つのデメリット
クラウドファンディングを活用するデメリットは次の2つです。
- 返金されないリスク
- 各種トラブルの発生リスク
それぞれ詳しく解説します。
1.返金されないリスク
クラウドファンディングは目標金額に到達していなくても、案件が実行されるものも少なくありません。
そのため、目標金額に到達しなかったら返金されるだろうと思っていると、案件によっては返金されないリスクがあります。
案件がどのような行動を取るのかは事前に記載されているため、投資する際は案件の内容をしっかりと確認することが大切です。
2.各種トラブルの発生リスク
各種トラブルの発生リスクがあることも、クラウドファインディンのデメリットです。
返礼品は指定されたタイミングで送付しなければなりません。
しかし、送付するまでに時間がかかり、遅延してしまうため、返礼品の納期遅延トラブルが発生するリスクがあります。
返礼品の納期遅延トラブルの事例は多いです。
そのため、納期遅延しないようにするためには、余裕を持った対応が求められます。
また、案件に投資してくれる支援者から様々なメッセージが送られてきます。
しっかりとメッセージへ返信しない場合、コミュニケーショントラブルが発生する他、トラブルが大きな問題となって案件が進まないケースも少なくありません。
コミュニケーショントラブルを発生させないためには、1つ1つ丁寧に返信し、真摯に対応することが大切です。
「クラウドファンディング 比較」でよくある質問
「クラウドファンディング 比較」でよくある質問は次の3つです。
- クラウドファンディングの仕組みとは?
- クラウドファンディングの種類とは?
- クラウドファンディングの流れとは?
それぞれの質問に対して回答していきます。
1.クラウドファンディングの仕組みとは?
クラウドファンディングはクラウドファンディングサイトを介して実施します。
起案者がサイトに案件を公開し、案件を見て支援したい支援者が資金を提供して支援する仕組みです。
クラウドファンディングの募集方式は大きく分けて、次の2つです。
- All in(オール・イン)方式:目標金額に到達しない場合でも資金調達できるものの、案件実施の確約が必要
- All or Nothing(オール・オア・ナッシング)方式:設定した目標金額に達した場合のみ資金調達が可能。目標金額に到達しない場合は資金調達ができません。
2.クラウドファンディングの種類とは?
クラウドファンディングの種類は次のとおりです。
- 購入型
- 融資型
- 株式型
- 寄付型
- ファンド型
- ふるさと納税型
上記のとおり、クラウドファンディングは様々な種類があり、種類によって特徴も異なるため、自社の案件に適したものを選択しなければなりません。
3.クラウドファンディングの流れとは?
クラウドファンディングの流れは「起案者」と「支援者」別に次のとおりです。
【起案者】
- 利用するクラウドファンディングサイトを選ぶ
- クラウドファンディングにて案件ページを作成する
- ページが完成したら案件を公開して資金調達を開始する
- 募集中にプロモーション活動を実施して案件ページを解散する
- 調達できた資金で案件を実行する
【支援者】
- クラウドファンディングサイトで案件を見る
- 気になる案件の内容・リターンなどを確認する
- 募集期間中にクラウドファンディングサイトを通じて支援をする
- 募集終了後に活動報告などで案件の進捗を確認する
- 予定どおりリターンが届くかを確認する
クラウドファンディングは支援者がいてこそであるため、支援者の立場になって取り組む必要があります。
クラウドファンディング 比較のまとめ
やみくもにクラウドファンディングサイトを利用してしまっては、案件成功率を向上させられません。
クラウドファンディングは様々な種類・サイトがあるため、自社案件に適したものでなければ、支援者の興味は惹けないからです。
そのため、当記事で解説したクラウドファンディングを比較する際のポイントも参考にしながら、自社に適したサイトを選ぶことが大切です。