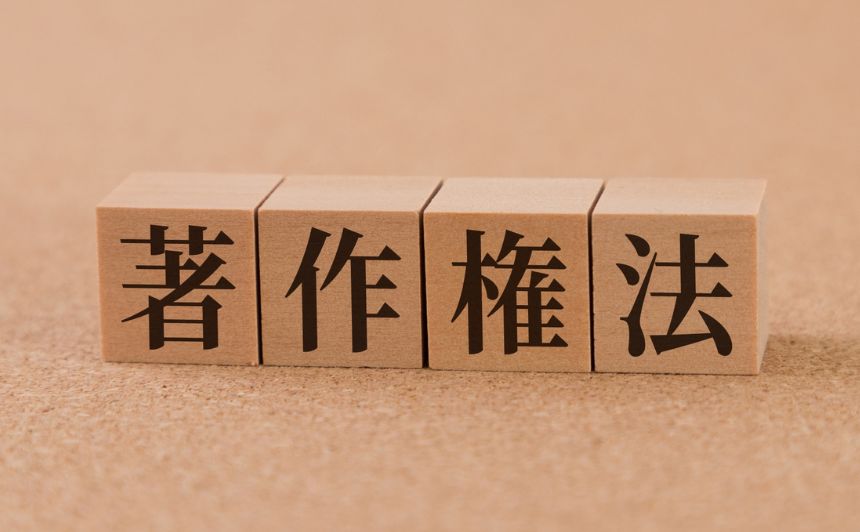著作権とは?
著作権とは、著作権法によって定められている著作物を制作した著作者に与えられる権利です。
ただし、著作者が制作したものすべてに著作権が与えられるわけではありません。
なぜなら、創作物と著作物は同義ではなく、創作物が著作物として認められない場合、著作権は与えられないからです。
創作物が著作物として認められるためには、次の4つの条件を満たしておく必要があります。
- 思想・感情が表現されている
- 著作者の個性が表現されている
- 何かを表現している
- 文芸・美術・学術あるいは音楽の範囲に属している
また、著作権は著作権法第17条の定めにより、「著作権(財産権)」と「著作者人格権 」の2種類で成り立っています。
著作権(財産権)
著作権(財産権)とは、財産権の1つで、1部もしくはすべてを譲渡・相続できる権利です。
著作権の譲渡については、著作権法第61条にて以下のように記されています。
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
著作権(財産権)の保護期間は原則著作者の死後70年間であり、それ以降はパブリック・ドメインとしても誰でも自由に利用できるようになります。
著作権(財産権)の主な権利
著作権(財産権)の主な権利は次のとおりです。
- 複製権
- 上映権
- 展示権
- 譲渡権
- 貸与権
- 二次的著作物の利用権
上記は代表的なものであり、他にも様々な権利があります。
著作者人格権
著作人格権とは、著作者のみが保有する権利で原則、著作者が死亡した際に消滅します。
著作人格権の主な権利は次のとおりです。
- 同一性保持権
- 公表権
- 氏名表示権
著作権と著作者人格権の大きな違いは、譲渡・相続の可否です。
前述のとおり、著作権は譲渡・相続が可能ですが、著作者人格権は譲渡・相続ができないため、契約を締結する際は注意する必要があります。
webサイトの著作権は制作者が持っている
著作権は著作物が制作された時点で自動的に制作者へ与えられる権利であり、所定の手続きは必要ありません。
webサイト制作の場合、画像や文章など著作権に該当するwebサイトのコンテンツの著作権は制作者に帰属されます。
したがって、自社で制作すればwebサイトの著作権を有しているのは自社ですが、webサイト制作会社などに制作を外注した場合、外注先がwebサイトの著作権を有するということです。
そのため、webサイトの制作を外注する場合は、契約書に著作権譲渡の旨を記載し、制作したwebサイトの著作権を自社に譲渡してもらう必要があります。
一方、著作者人格権は譲渡ができないため、自社で権利を保有できません。
著作人格権の場合は、契約書に著作人格権不行使条項を明記すれば、外注先が著作者人格権を行使できなくなります。
著作権に該当するwebサイトのコンテンツ
著作権に該当するwebサイトのコンテンツは次の6つです。
- 画像
- 動画
- 音楽
- 文章
- 設計書・ソースコード
- デザイン・テンプレート
それぞれ詳しく解説します。
画像
webサイトに使用されている画像は制作者の個性・思想が表現されているため、著作権に該当するコンテンツの1つです。
ただし、すべての画像が著作権の対象となるわけではありません。
webサイトに掲載されている画像のうち、イラスト・写真などは著作権の対象となりますが、グラフ・表は著作権の対象とはならないため、注意が必要です。
動画
ネット回線やweb技術の進歩で、動画を使用しているwebサイトも多いですが、webサイトに掲載されている動画も著作権の対象です。
また、動画制作に当たっては撮影・編集などが必要ですが、その過程も著作権が認められている他、映像に使用されているイラストや音楽なども著作権の対象となります。
音楽
webサイトで使用されている音楽・効果音も著作権に該当するコンテンツの1つです。
音楽・効果音を自社で制作した場合は自社、外注先が制作した場合は外注先が著作権を有しています。
また、近年はフリー素材として提供されている音楽・効果音を使用しているwebサイトが増えています。
フリー素材の場合は著作権フリーだと思われがちですが、利用にあたっては利用規約や条件を設けているフリー素材サイトも少なくありません。
規約・条件に違反している場合は著作権侵害に該当する恐れがあるため、フリー素材を使用する際は利用規約をしっかりと確認する必要があります。
また、無名・有名にかかわらず、アーティストの曲は著作権が厳しいため、著作権者の許諾がない場合は利用してはいけません。
文章
webサイトに掲載されているコラム・記事などの文章も著作権に該当するコンテンツです。
他のコンテンツ同様、自社が文章を制作した場合は自社、外注先が文章を制作した場合は外注先が著作権を有します。
また、SEO記事やweb記事などをライターに外注した場合は、執筆したライターが著作権を有します。
設計書・ソースコード
設計書は著作権の対象となる場合もあれば、対象とならない場合もあります。
他コンテンツと違い、個別の判断が必要なため、注意が必要です。
ソースコードには一定の決まりがあるため、思想・個性が反映されにくいといわれています。
そのため、著作権が認められない可能性は高いですが、まったく認められないというわけではありません。
デザイン・テンプレート
webサイトのデザインも著作権に該当するコンテンツの1つです。
また、フリー素材を上手く活用してwebデザインを制作する際、既存の著作物を選択して配列した場合は編集者著作物となります。
また、事前に用意されているデザインテンプレートも著作権に該当するコンテンツであり、著作権は外注先が保有しています。
著作権侵害の条件
画像や動画、音楽、文章、設計書・ソースコード、デザイン・テンプレートなどは著作物として著作権が生じる可能性があります。
一方、HTMLやCSS、グラフ・表、ドメイン、規約などの要素は、著作権が認められる可能性が低いです。
そのため、webサイト制作時に制作されたすべての要素に著作権が生じるわけではありません。
ただし、著作物として著作権が認められるか、認められないかはケースバイケースであり、最終判断は裁判所に委ねられます。
また、自分で撮影した写真であっても被写体によっては商標権・肖像権の問題、キャッチコピー・ドメインは商標権侵害や不正競争防止法違反のリスクがあるため、注意が必要です。
webサイトの著作権違反に対する罰則
webサイトの著作権を侵害した場合、著作権法違反により、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に科される可能性がある他、著作権者から損害賠償や不当利得返還などを請求されるケースがあります。
また、著作者人格権や実演家人格権を侵害した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に科させる恐れがあります。
webサイトの著作権を侵害しないための対策
webサイトの著作権を侵害しないための対策は次の4つです。
- 著作権譲渡契約を締結する
- ライセンス契約を締結する
- 利用規約を理解したうえでフリー素材を活用する
- CMSを利用する
それぞれ詳しく解説します。
著作権譲渡契約を締結する
webサイトの著作権を有しているのはwebサイト制作依頼者ではなく、webサイト制作者です。
著作権侵害を防止するためには、著作権者であるwebサイト制作者と著作権譲渡契約を締結し、著作権を譲渡してもらう必要があります。
条件を細かくすれば、財産権の1部のみを譲渡できるため、双方協議のうえ、納得いく形で契約締結していくとよいです。
ライセンス契約を締結する
ライセンス契約とは、著作権の権利者が第三者に対して著作物の使用を認める契約のことです。
ライセンス契約を締結すれば、著作権を保持していなくても、著作権侵害にはなりません。
ただし、ライセンス契約は利用範囲や利用期間、利用条件、利用料などが定められています。
利用範囲を超えてしまうと著作権侵害となるため、注意が必要です。
利用規約を理解したうえでフリー素材を活用する
フリー素材とは、写真や音楽、映像など、誰でも自由に利用できるコンテンツのことです。
ただ、フリー素材も利用規約が定められていることが多く、商用利用が認められていなかったり、利用先にて素材配信元・著作権者情報を記載する必要があったりします。
利用規約に遵守していない場合、著作権侵害に該当してしまうため、フリー素材は利用規約を理解したうえで活用しなければなりません。
CMSを利用する
CMSを利用してwebサイトを制作するのも、著作権を侵害しないための対策の1つです。
自社でイチからwebサイトを構築する場合、他のwebサイトと内容やソースコードがかぶってしまい、著作権を侵害してしまうリスクがあります。
CMSであれば構築されたwebサイトをそのまま使用できるように設計されているため、著作権を侵害するリスクを低減しながら、魅力的なwebサイトを制作可能です。
webサイト制作 著作権でよくある質問
webサイト制作 著作権でよくある質問は次の4つです。
- 著作権の譲渡を断わられるケースもある?
- 制作料金を支払ったら著作権は譲渡されますか?
- コピーライトとは?
- 著作権で行われる民事上の手続きとは?
それぞれ詳しく解説します。
1.著作権の譲渡を断わられるケースもある?
著作権譲渡について対応していたことがない、CMSなどを利用していて著作権譲渡ができないと思っているなどの理由から、著作権の譲渡を断られるケースが少なからずあります。
webサイト制作完了後に著作権の譲渡を断られないためには、契約時にwebサイトの著作権を譲渡してもらえるか確認しておかなければなりません。
2.制作料金を支払ったら著作権は譲渡されますか?
制作料金を支払ったからといって、著作権は譲渡されません。
制作料金はwebサイト制作業務への対価であり、著作権移転への対価とは解約されないからです。
そのため、契約書に著作権譲渡に関する記載がない場合、制作料金を支払っただけでは、著作権は譲渡されません。
確実に著作権を譲渡するためには、契約書に著作権譲渡について明記しておくことが大切です。
3.コピーライトとは?
コピーライト(Copyright)とは、著作権と同じ意味を持っています。
webサイトにCopyright表記(略して「©」と表示することも可能)しておけば、著作権を有していることを示して警告が可能です。
webサイト制作時点で著作権が発生するとみなされるため、Copyrightを表記していなくても著作権の主張は可能です。
しかし、Copyrightを表記していれば、トラブル防止につながります。
特にこだわりがないのであれば、Copyrightを表記しておくことをおすすめします。
4.著作権で行われる民事上の手続きとは?
著作権で行われる民事上の手続きは次の4つです。
| 侵害の差し止め | すでに起きている・これから起こるリスクのある侵害行為をやめるように求める |
| 名誉回復措置 | 社会的影響が大きい有名人などが著作権違反により、評判などを大きく損ねた場合、それらを回復する措置を求める |
| 損害賠償 | 損害の規模を金銭に換算して請求すること |
| 不当利得返還 | 著作権侵害により不当な利益を得て被害者に損失を与えたとして、得た利益を被害者へ返還する必要がある |
損害賠償請求する場合、どの程度損害があるのか被害者は証明しなければなりません。
損害額の算出が難しい場合、「ライセンス費用相当」「著作権侵害者が得た金額」「商品価格×無断譲渡数」のいずれかの方法で算出することが認められています。
webサイト制作 著作権 まとめ
webサイトの著作権はwebサイト制作を依頼した方が保有していると考えている方は多いです。
しかし、当記事で解説したとおり、webサイト制作を外注した場合、webサイトの著作権を保有するのは外注先です。
したがって、外注によって完成したwebサイトの著作権を自社で保有するためには、著作権譲渡条項などを契約書に明記し、著作権を譲渡してもらえるよう取り決めておく必要があります。
また、自社でwebサイトを制作する場合、気付かないうちに著作権侵害に陥るリスクがあります。
当記事で解説した著作権の対象となるコンテンツも参考にしながら、著作権侵害していないかしっかりと確認しておくことが大切です。
みやあじよも「売上あげる、お手伝い」をコンセプトに、著作権に留意しながらECサイトやコーポレートサイトなどのサイト制作、アクセス解析をはじめとするSEO支援などを行っています。集客支援も手伝ってくれるWebサイト制作会社への依頼を検討している方は、みやあじよにご相談ください。