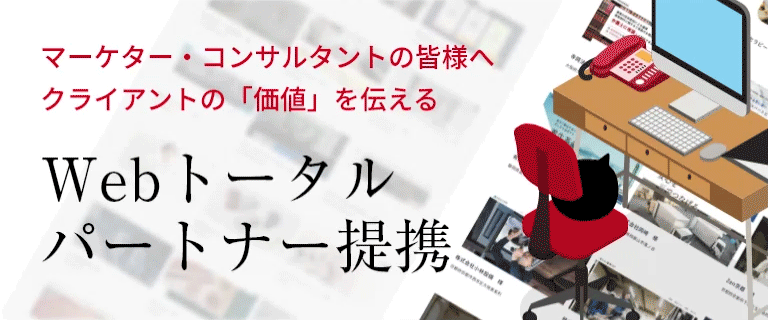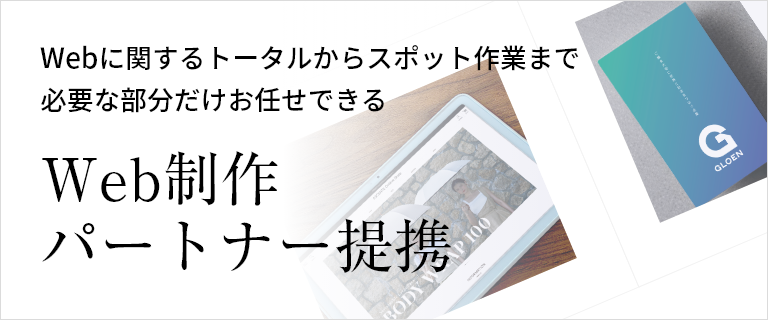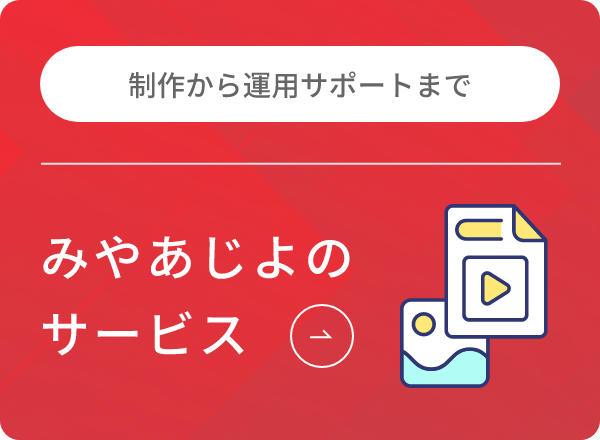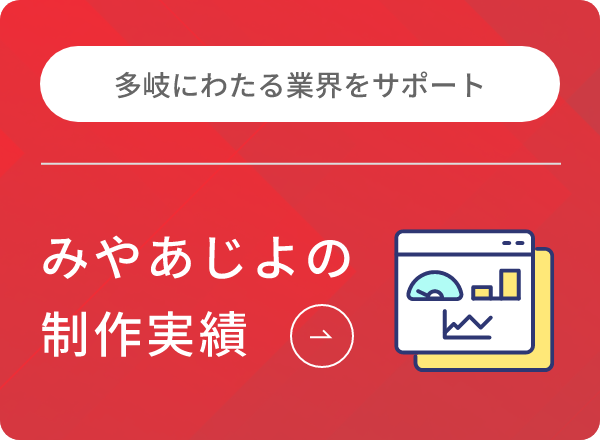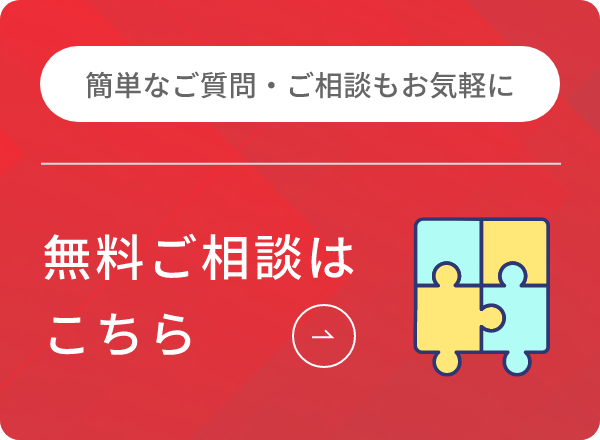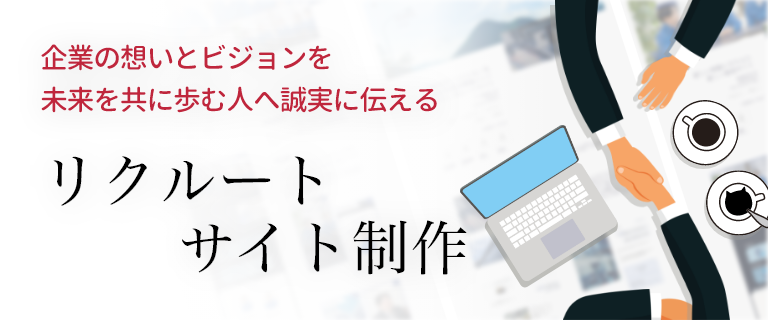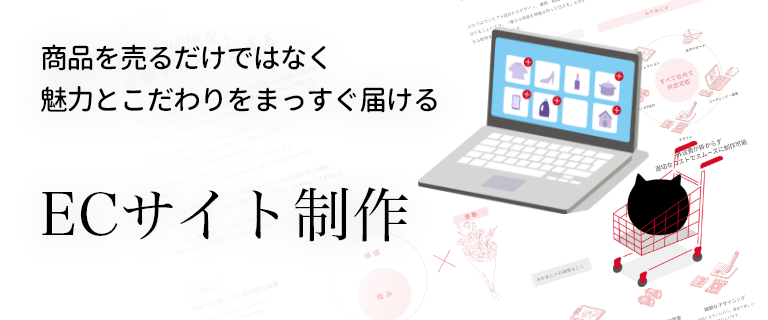webサイト制作で申請できる補助金ってどんな種類があるんだろう?
この記事ではwebサイトをお得に作るための補助金をご紹介します。
目次
webサイト制作で利用できる補助金4選
webサイト制作で利用できる補助金は次の4つです。
- 事業再構築補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり補助金
- 地方自治体の補助金
それぞれ詳しく解説します。
1.事業再構築補助金
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスによる社会変化に対応するため、中堅企業・中小企業の事業の再構築を支援する補助金です。
事業再編や事業・業種転換など、幅広い事業が補助対象となっている他、給付金額が大きいため、思い切った事業再構築が可能です。
ただし、申請に関しては「売上減少」「事業再編や新分野転換などへの取り組み」「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定」の3要件を満たす必要があります。
2.小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓などの取り組みや販路開拓と合わせて実施する業務効率化などに要する1部経費を補助する補助金です。
小規模事業者持続化補助金の補助対象となるのは、小規模事業者もしくは、一定要件を満たす特定非営利活動法人です。
そのため、一定以上の規模を持つ中小企業の場合は利用できません。
3.ものづくり補助金
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)とは、webサイト制作といったシステム構築費や生産プロセス改善を目的とした設備投資といった事業経費などを補助してくれる補助金です。
補助対象は中小企業・小規模事業者(個人事業主含む)、対象業種は製造業や旅行、ソフトウェアなどと幅広いため、補助目的と合致していれば多くの企業が利用できます。
4.地方自治体の補助金
地方自治体が独自に実施している補助金もあります。
国が運営している補助金と比べると、給付額が低い場合もありますが、webサイト制作だけでなく、周辺機器やコンテンツリニューアルにかかるコストまでカバーしてくれるものも多いです。
国が運営している補助金が利用できないという場合、地方自治体の補助金に目を向けてみるのも1つの手段といえます。
webサイト制作で補助金を利用する際の注意点
各種補助金は業務効率化や販路の開拓を主な目的としています。
そのため、webサイトのリニューアルや販路開拓が目的ではないwebサイト制作は、補助の対象外となるリスクが高いです。
また、販路開拓が目的であったとしても、掲載コンテンツが会社概要や社内向けブログしかないwebサイトの場合も対象外となる可能性が高いです。
webサイト制作で補助金を利用する際は、自社が制作を検討しているwebサイトが補助対象となるかどうかしっかりと把握しておかなければなりません。
webサイト制作で補助金を利用するステップ
webサイト制作で補助金を利用するステップは次のとおりです。
- 申請する補助金の選択
- 補助金の概要確認・必要書類の準備
- 申請手続き
- 採択通知・交付申請
- 事業の実施・補助金の交付
それぞれ詳しく解説します。
1.申請する補助金の選択
まずは自社の規模や事業形態、補助を受ける事業の目的などを照らし合わせながら、申請する補助金を選択します。
ただし、補助金は様々な種類があるため、どのような補助金があるのか把握しておかないと、自社に最適な補助金を選択できません。
最適な補助金を選択するのにおすすめなのが「ミラサポplus」です。
ミラサポplusは中小企業庁が提供している補助金・助成金の検索サイトで、制度内容だけでなく活用事例などの掲載や、電子申請の支援もしています。
2.補助金の概要確認・必要書類の準備
申請したい補助金が決まったら、補助金の概要を確認し、申請に必要な書類の準備をしていきます。
準備する書類は応募申請書や事業計画書などが一般的です。
しかし、補助金によって必要書類は異なる他、書類によっては準備までに時間を要してしまうものもあります。
期限に間に合わないという事態を避けるためには、しっかりと内容を確認したうえで早めに書類準備に取り掛からなければなりません。
3.申請手続き
申請の準備が終了したら、提出期限までに事務局へ書類一式を提出します。
提出方法は「書面郵送」と「電子申請」の2種類があり、申請する補助金によって提出方法は異なります。
書面郵送の場合、事務局に届くまでに時間を要するため、期限ぎりぎりになってしまうと、間に合わないという事態になりかねません。
このような事態を避けるためには、公募要領をしっかりと確認しておく必要があります。
4.採択通知・交付申請
補助金の申請後、審査を通過できたら、所定の方法で採択通知が届きます。
採択通知が届いた後、交付申請を実施し、交付申請が認可されれば、補助対象となる事業の実施が可能です。
5.事業の実施・補助金の交付
交付申請が認可された後、申請した内容の事業を実施し、事業内容や経費を事務局に申請をします。
申請確認が完了次第、申請内容をもとに補助金額を算出、補助金が確定したら、事務局より補助金が交付されます。
そもそも補助金とは?
補助金とは、国・自治体の政策に合わせて募集される制度のことです。
これまで紹介してきたとおり、補助金には様々な種類があるため、経営計画や事業内容などと照らし合わせながら、自社に最適な制度を利用できます。
他の給付制度と比べると補助額が高めに設定されているのがメリットですが、審査が厳しく採択率が低いというデメリットもあるため、利用する際は慎重に検討する必要があります。
管轄省庁は経済産業省で、財源は税金であることも補助金の大きな特徴です。
助成金との違い
助成金は厚生労働省が管轄し、雇用保険料が財源となっている制度です。
補助金と同様、申請後には審査があるため、必ず受け取れるものではありません。
ただし、補助金と比べると審査が厳しくないため、ハードルが低く、比較的利用しやすい制度といえます。
制度の仕組みに違いはないものの、補助金と助成金では管轄省庁および財源が大きく異なります。
給付金との違い
給付金とは、国・自治体が個人・事業者に向けて支給する制度です。
明確な区分はありませんが、事業展開している事業者を対象とするのが補助金・助成金であるのに対して、給付金は個人を対象としたものが多いです。
また、要件さえ満たしていれば、基本支給されているため、他制度と比べると利用しやすく、支援を受けやすいといえます。
ただし、給付金の中にも審査が必要なものもあるため、利用前に概要を確認しておかなければなりません。
補助金を利用する際の4つの注意点
補助金を利用する際の注意点は次の4つです。
- 必ず採択されるとは限らない
- 申請の手間がかかる
- 補助金は事業実施後に支給される
- 返還リスクがある
それぞれ詳しく解説します。
1.必ず採択されるとは限らない
補助金には審査があるため、申請したからといって必ず採択されるわけではありません。
また、補助金は与えられた予算があり、募集枠への応募数などによって採択率が変わります。
そのため、採択率を少しでも高めたいというのであれば、中小企業診断士やコンサルタントなどに依頼し、サポートを受けながら申請することをおすすめします。
2.申請の手間がかかる
補助金は事業計画書などの提出が求められるため、申請に手間がかかることがほとんどです。
特に事業計画書を実務で作成した経験がない場合、法律用語などを解読しながら書類の準備をしなければならないため、想定よりも時間がかかるリスクが高いです。
また、時間をかけて準備した書類が受給要件を満たしておらず、受給できなかったという事態も避けなければなりません。
書類作成に不慣れで申請に不安があるという場合は、補助金について相談できる相手を探しておくことをおすすめします。
3.補助金は事業実施後に支給される
補助金は事業に使用した経費を計上して申請した後、補助額が決定されて交付される後払いがほとんどです。
仮に500万円の事業で3/4の補助を受ける場合でも、まずは自己資金で500万円支払わなければならないため、「補助金を利用する=自己資金がいらない」というわけではありません。
そのため、申請前には事業に必要な分の資金を確保しておくことが大切です。
4.返還リスクがある
補助金には補助金適正化法というものがあり、各種違反行為が定められています。
具体的な違反行為としては「発注日の改ざん」や「領収書内容を水増して補助金を多く受け取る」ことなどが挙げられます。
違反行為による不正受給が発覚した場合、補助金を全額返金しなければならない他、全額返還するまでは返還していない額の10.95%が年間で加算されます。
不正受給はリスクが大きいため、絶対にやってはいけません。
補助金の採択率を上げる2つのポイント
補助金の採択率を上げるポイントは次の2つです。
- 加点審査項目を盛り込む
- 規定に沿った申請書類を用意する
それぞれ詳しく解説します。
1.加点審査項目を盛り込む
小規模事業者持続化補助金の採択率は平均8割程度と決して低くありませんが、採択率を上げたいのであれば、もうひと手間加える必要があります。
そこでおすすめしたいのが、加点審査項目の盛り込みです。
加点審査項目とは、自社の製品・サービスの強みや、Webサイトの目標・運用体制、市場動向などのことです。
これら項目を可能な限り数値化して、経営計画書などに盛り込めば、内容が適正であると判断され、採択される確率が上がります。
また、グラフや表にまとめれば、より分かりやすく情報を伝えられるため、採択率をさらに高められる可能性があります。
2.規定に沿った申請書類を用意する
規定に沿った申請書類を用意することも、採択率を上げるためには欠かせないポイントです。
各種申請書類のフォーマットは補助金の各ホームページに記載されています。
漏れのないように準備し、不備のないように書類を作成することも、採択率を上げるためには欠かせません。
webサイト制作 補助金でよくある質問
webサイト制作 補助金でよくある質問は次の2つです。
- webサイト制作の費用相場を教えてください。
- 補助金を利用するメリットとは?
それぞれ詳しく解説します。
1.webサイト制作の費用相場を教えてください。
webサイト制作の費用相場は次のとおりです。
- WordPressの設置:3万円~
- テンプレートデザイン:3万~10万円程度
- オリジナルデザイン:20万~100万円程度
- ECサイト制作:50万円以上
- 独自システムの構築:100万円以上
このように制作するwebサイトによって費用相場は大きく異なる他、webサイトの種類や規模、実装する機能、制作の依頼先によっても費用は大きく変動します。
webサイトの費用対効果を最大化するためには、相見積もりを実施したうえで自社と相性がよい制作会社を選定しなければなりません。
2.補助金を利用するメリットとは?
補助金を利用するメリットは次の3つです。
- webサイトの質を高められる
- 事業計画策定の手助けとなる
- 事業にかかる費用負担を軽減できる
- 人脈拡大の機会を得られる
補助金を利用すれば、事業にかかる経費の1部を補助してくれるため、結果として費用負担を軽減できます。
費用負担を軽減できれば、システム開発やwebマーケティングに強い会社にWebサイト制作を依頼できるため、質の高いwebサイト制作が可能です。
また、補助金によっては支援事業者が必要だったり、商工会・商工会議所のサポートを受けれたりします。
そのため、補助金の利用をきっかけに専門家や相談員と人脈を築けます。
商工会・商工会議所は補助金相談以外にも説明会・セミナーなどを開催しているため、補助金の利用をきっかけに参加・交流の機会が増えれば、人脈の拡大も可能です。
webサイト制作 補助金 まとめ
webサイト制作で利用できる補助金は「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」など、様々なものがあります。
ただし、補助金は業務効率化や販路の開拓を主な目的としているため、社内ブログなど目的にそぐわない1部webサイトの場合は補償対象外となる可能性が高いです。
また、補助金は「必ず採択されるとは限らない」「申請の手間がかかる」など、利用する際の注意点も少なくありません。
そのため、補助金を利用する際はメリット・デメリットを理解したうえで利用を検討し、利用する際は公募要領などをしっかりと把握したうえで、準備を進める必要があります。
みやあじよも「売上あげる、お手伝い」をコンセプトに、webサイト制作はもちろん、アクセス解析をはじめとするSEO支援などを行っています。IT導入補助金のサポートもしているため、補助金を活用してWebサイト制作会社への依頼を検討している方は、みやあじよにご相談ください。